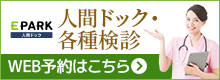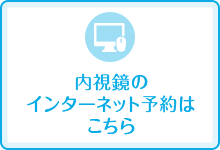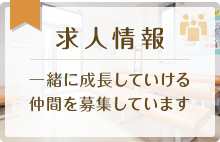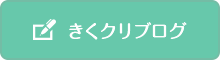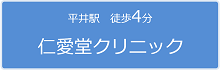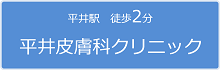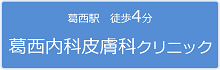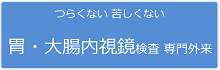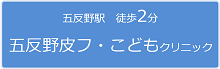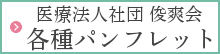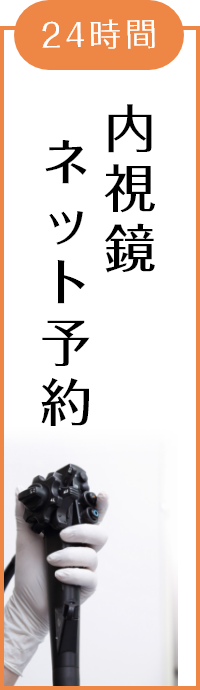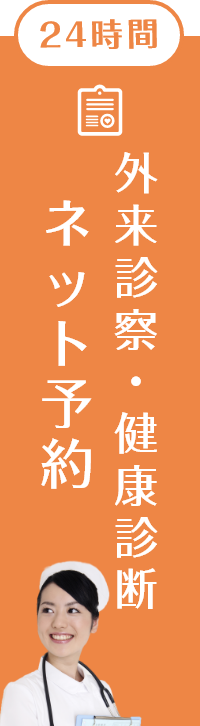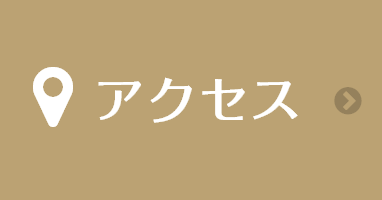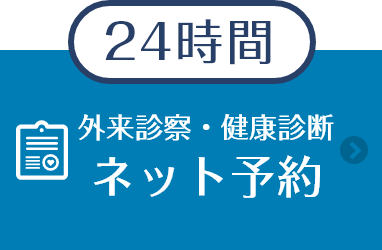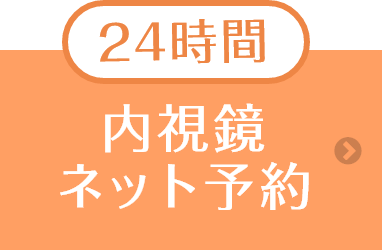秋の季節になりましたね
美味しいものがたくさんありますが、ノロウィルスはとても辛いです
今回のブログではノロウィルスについてお伝えします

 ノロウィルスとは?
ノロウィルスとは?
ノロウィルスは、私たちのお腹(小腸)の中で増える、とても小さなウィルスです。
冬場(主に11月~2月頃)に流行し、「感染性胃腸炎」や「食中毒」の主な原因となります。
このウィルスのいちばんの特徴は、なんといっても「感染力の強さ」です。
ほんの少しのウィルスが体の中に入るだけで感染してしまうため、ご家族の誰かがかかると、
あっという間に家庭内に広がってしまうことも少なくありません。
 症状の特徴
症状の特徴
ノロウィルスに感染すると、平均して1日~2日(24~48時間)の「潜伏期間」を経て、次のような症状が突然現れます。
・突然の吐き気、嘔吐(おうと)
・下痢(水のような便)
・腹痛(お腹がシクシク痛む、差し込むような痛みなど)
・発熱(37℃~38℃程度のことが多いですが、高熱になることもあります)
これらの症状は、健康な大人であれば、通常1~2日ほどで自然に落ち着いてくることがほとんどです。
ただし、症状が治まった後も、1週間~長いと1ヶ月ほどは便の中にウィルスが排出され続けることがあるため、注意が必要です。
 ノロウィルスが起こる原因
ノロウィルスが起こる原因
ノロウィルスの感染経路は、ウィルスが「口から入る」こと(経口感染)です。
主な原因は、大きく分けて2つあります。
食品からの感染(食中毒) ウィルスに汚染された二枚貝(カキ、アサリ、シジミなど)を、生や、加熱が不十分な状態で食べた場合に起こります。
人からの感染(二次感染)
・接触感染: 感染した人の便や吐しゃ物に直接触れたり、ウィルスが付着したドアノブや手すりなどに触れたりした後、その手で口に触れることで感染します。
・飛沫(ひまつ)感染・塵埃(じんあい)感染: 感染した人の吐しゃ物や便が乾燥すると、細かな粒子となって空気中に舞い上がることがあります。これを吸い込むことでも感染します。
 ノロウィルスの種類
ノロウィルスの種類
実は、ノロウィルスにはたくさんの「遺伝子の型(タイプ)」があります。インフルエンザにA型やB型があるように、
ノロウィルスにも多くの種類が存在するのです。 そのため、一度ノロウィルスにかかって免疫ができたとしても、別の型のノロウィルスには感染してしまう可能性があります。
「去年もかかったから大丈夫」というわけにはいかず、毎年注意が必要になるのです。
 ノロウィルスの発生部位ごとの特徴
ノロウィルスの発生部位ごとの特徴
・食品(主に二枚貝)を介する場合: ノロウィルスは、海水中などに存在することがあります。
二枚貝は大量の海水を取り込んでプランクトンなどを食べるため、その際にウィルスも一緒に取り込み、内臓(中腸腺)に蓄積してしまうことがあります。
貝自身はノロウィルスで病気になるわけではありませんが、私たちがそれを食べることで感染してしまいます。
・人を介する場合(二次感染): こちらが非常に多い感染経路です。感染した人の吐しゃ物や便には、目には見えないほど大量のウィルスが含まれています。
例えば、トイレの後で手を洗うのが不十分だったり、吐しゃ物の処理がうまくできなかったりすると、手や周囲の環境にウィルスが広がってしまいます。
ノロウィルスは乾燥にも強いため、カーペットなどで乾燥したウィルスが舞い上がり、感染が広がるケースも多く報告されています。
 ノロウィルスを引き起こす主な疾患
ノロウィルスを引き起こす主な疾患
ノロウィルスに感染することで引き起こされる主な病気は**「感染性胃腸炎」です。食中毒として扱われることもあります。
ほとんどの場合は数日で回復に向かいますが、特に小さなお子様やご高齢の方、もともと持病がある方などは、注意が必要です。
嘔吐や下痢が続くと、体から水分と電解質(塩分やカリウムなど)が失われ、「脱水症状」を引き起こしやすくなります。
脱水症状がひどくなると、ぐったりして元気がなくなったり、場合によっては入院が必要になったりすることもあります。
 ノロウィルスを和らげるために自分でできる対処法は?
ノロウィルスを和らげるために自分でできる対処法は?
1. 水分補給(脱水予防)
嘔吐や下痢が続くと、体は水分不足になります。一度にたくさん飲むと吐き気を誘発してしまうため、**「こまめに、少しずつ」**が鉄則です。
おすすめは、体に吸収されやすい「経口補水液」です。もし無ければ、スポーツドリンクや湯冷まし、麦茶などでも構いません。
吐き気が強い時は無理をせず、症状が少し落ち着いてから、スプーン1杯程度から試してみましょう。
2. 食事
無理に食べる必要はありません。食欲が出てきたら、おかゆや、やわらかく煮込んだうどん、すりおろしたりんごなど、お腹にやさしい(消化の良い)ものから始めましょう。
3. 感染を広げないための対処(二次感染の予防)
もしご家族が吐いてしまったら、その処理には細心の注意が必要です。
アルコール消毒はノロウィルスには効きにくいとされています。
必ず使い捨ての手袋、マスク、エプロン(無ければゴミ袋で代用)を着用します。
吐しゃ物はペーパータオルなどで静かに拭き取り、すぐにビニール袋に入れて口を縛ります。
拭き取った後は、家庭用の塩素系漂白剤を薄めた液で、床や周囲を浸すように拭き取り、その後水拭きします。
手洗いは、石鹸を使って30秒以上かけて指の間や手首まで丁寧に洗い、流水でしっかり流しましょう。
 受診をした方が良い場合は?
受診をした方が良い場合は?
・水分がまったく摂れない、または飲んでもすぐに吐いてしまう
・ぐったりしていて元気がない、意識がもうろうとしている
・尿の量が極端に少ない、または半日以上出ていない
・唇がカサカサに乾いている、泣いても涙が出ない(お子様の場合)
・嘔吐や下痢が3日以上続いている
・血便(便に血が混じる)が出る
・お腹の痛みがだんだん強くなる
 どのような検査が必要で、何を調べる?
どのような検査が必要で、何を調べる?
医療機関では、必ずしも全員に検査が行われるわけではありません。
流行状況や症状から、医師が「ノロウィルスによる胃腸炎の可能性が高い」と判断することが多いためです。
 どのような診断と治療が行われるの?
どのような診断と治療が行われるの?
周り(家族、職場、学校など)に同じような症状の人はいませんか?
症状が出る前に、何か思い当たる食べ物(特にカキなど)を食べましたか?
その後、お腹の音を聞いたり(聴診)、お腹を押さえて痛みの場所や強さを確認したり(触診)といった診察が行われます。
問診や診察、必要に応じて行った検査の結果から「ノロウィルス感染症」と診断されます。
前述のとおり、ノロウィルスに直接効くお薬はないため、治療はつらい症状を和らげる「対症療法」となります。
脱水症状がひどいと判断された場合は、点滴(輸液)で直接体に水分や電解質を補給する処置が行われます。
 最後に…
最後に…
ノロウィルスは、突然のつらい症状で心も体も疲弊させてしまう病気です。しかし、ほとんどの場合は数日で回復に向かいます。
もし感染してしまったら、焦らずに「水分補給」を第一に考えて、ゆっくりと休んでください。
そして、ノロウィルスは「予防」がとても大切です。流行シーズンは特に、「食事の前」「トイレの後」の石鹸による丁寧な手洗いを徹底しましょう。
食品、特に二枚貝は中心部までしっかり(85℃~90℃で90秒以上)加熱することを心がけてください。 正しい知識で対処して、つらい冬の感染症を乗り切りましょう!!
監修:俊爽会 理事長
日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医
日本内科学会 総合内科専門医 小林俊一





 栄養指導
栄養指導
















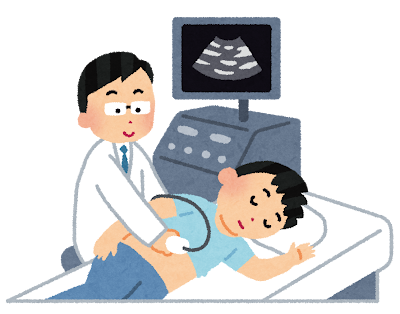


 ノロウィルスとは?
ノロウィルスとは?