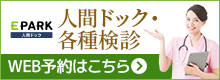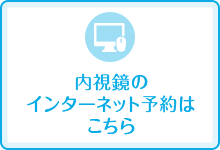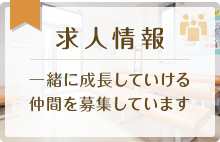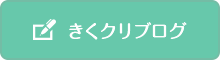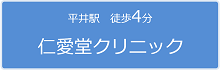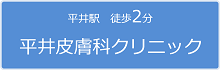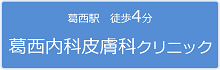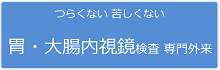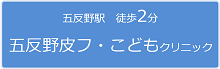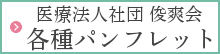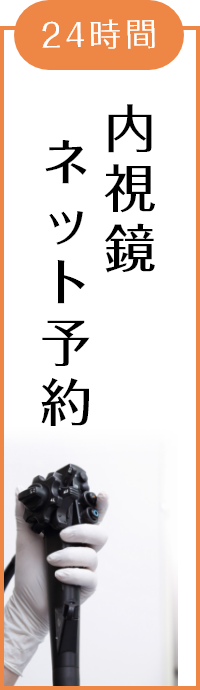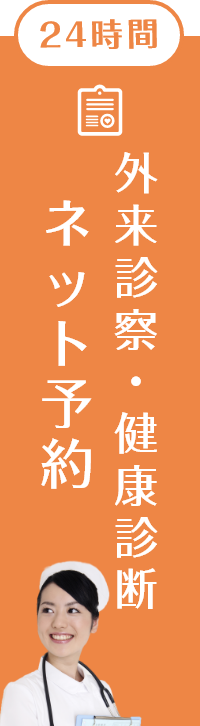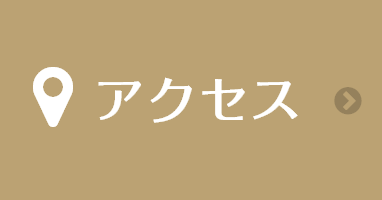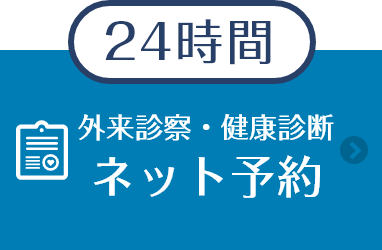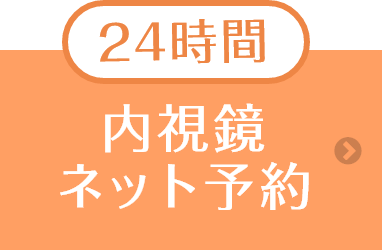その肌トラブル、皮膚科へ相談を!受診の目安と早期治療の重要性
2025.07.18更新
「こんな症状で皮膚科に行っていいのかな?」肌のトラブルで迷った経験はありませんか?
自己判断での対処は、症状を悪化させたり、治りを遅らせたりする可能性があります。
どのような肌の症状のときに皮膚科を受診すべきか、その目安と早期治療の重要性について解説します。
ご自身の肌の健康を守るため、ぜひ参考にしてください。
1. こんな症状は要注意!皮膚科を受診すべきサイン
皮膚の症状は多岐にわたりますが、特に以下のようなサインが見られたら、早めに皮膚科を受診することをおすすめします。
1-1. 治まらないかゆみ、赤み、腫れ
一時的なかゆみや赤みはよくありますが、数日経っても治まらない、あるいは悪化している場合は注意が必要です。
アトピー性皮膚炎や湿疹、接触性皮膚炎などの可能性があります。慢性化する前に適切な治療を受けることが大切です。
1-2. 発疹、水ぶくれ、ただれ、かき壊しがある
原因不明の発疹が広がる、水ぶくれができている、皮膚がただれている、また、かゆみで掻き壊してじゅくじゅくしている状態は、細菌やウイルスの感染、重度の湿疹などが考えられます。
自己判断での市販薬の使用は、かえって症状を悪化させるリスクがあるため避けましょう。
1-3. 繰り返すじんましんやアレルギー症状
特定の食べ物や物質に触れてじんましんが繰り返し出る、あるいは原因不明のじんましんが全身に出る場合は、アレルギー反応の可能性があります。
専門的なアレルギー検査を含め、医師による診断が不可欠です。
菊川内科皮膚科クリニックではView39というアレルギー検査を導入しております。
View39は、39種類の主要なアレルゲンに対する特異的IgE抗体を、一度の少量の採血で調べられる新しいアレルギー検査です。
花粉や食物、動物、ダニなど幅広い項目を網羅し、原因不明のアレルギー症状の特定や治療方針決定に役立ちます。
1-4. 治らないニキビや吹き出物
ニキビや吹き出物は、適切な治療を行わないと悪化してニキビ跡が残ってしまうことがあります。
炎症が強いニキビや広範囲にわたるニキビは、皮膚科での治療が効果的です。自己流のケアには限界があります。
1-5. 強めの症状が出る虫刺され
通常の虫刺されは自然に治まりますが、異常に腫れ上がったり、激しい痛みを伴ったり、患部が広範囲に及んだりする場合は、アレルギー反応や細菌感染の可能性があります。
特に、掻き壊しから「とびひ」になることもあるため、早めの処置や投薬が重要です。
1-6. 爪や髪の毛の異変
爪の変色や厚み、もろさは爪白癬(水虫)の可能性があり、検査が必要な場合があります。
髪の毛では手櫛で髪が大量に抜ける、部分的に円形脱毛症が起きている、AGA(男性型脱毛症)などがある場合は要注意です。
見た目の問題だけでなく、早期治療が大切な疾患もありますので、気になる場合はご相談ください。
1-7. 市販薬で改善しない、悪化する症状
市販薬を使っても症状が良くならない、むしろ赤みやかゆみが増した場合は、その薬が症状に合っていないか、より専門的な治療が必要なサインです。
自己判断での使用を中止し、皮膚科を受診してください。
1-8. 原因不明の皮膚症状や全身症状
明らかな原因が分からない皮膚症状や、発熱、倦怠感などの全身症状を伴う皮膚トラブルは、内臓疾患のサインである可能性もゼロではありません。
このような場合は、速やかに医療機関を受診してください。
2. 「これくらいで…」と思わないで!早期受診のメリット
「こんな軽い症状で皮膚科に行っていいのかな?」とためらう方もいますが、皮膚トラブルにおいては早期受診が非常に重要です。
2-1. 症状の悪化を防ぎ、早く治る
皮膚の症状は、放置すると悪化し、治療に時間がかかったり、痕が残ったりするリスクが高まります。
初期の段階で適切な診断と治療を受けることで、症状の悪化を防ぎ、より早く治すことができます。治療期間の短縮や費用負担の軽減にもつながる場合があります。
2-2. 正しい診断と適切な治療
皮膚科医は、豊富な知識と経験、そして専門機器を用いて、肉眼では見えない部分まで詳しく診察し、正確な診断を下します。
その診断に基づき、症状に合った最適な治療法(内服薬、外用薬、処置など)を提案することができます。自己判断では難しい、的確な治療が受けられます。
2-3. 自己判断による悪化や痕残りを防ぐ
誤った自己判断や不適切な市販薬の使用、間違ったケアは、かえって症状を悪化させたり、色素沈着や瘢痕などの痕を残してしまうことがあります。
専門家による適切な治療を受けることで、このようなリスクを回避し、きれいに治すことが期待できます。
3. 皮膚科ではどんなことをするの?主な検査と治療
皮膚科を受診すると、一般的に以下のような流れで診察が進みます。
3-1. 丁寧な問診と視診
いつから、どのような症状があるのか、かゆみや痛みはあるか、他に持病があるかなどを詳しくお伺いします。
その後、患部を直接目で見て詳しく状態を確認します。
3-2. 必要に応じた検査
診断のために、以下のような検査を行うことがあります。
ダーモスコピー: ほくろやシミ、皮膚がんなどの鑑別に用いる特殊な拡大鏡です。
アレルギー検査: 血液検査などで、アレルギーの原因物質を特定します。
真菌検査: 水虫などのカビによる疾患が疑われる場合、皮膚の一部を採取して顕微鏡で調べます。
3-3. 薬による治療と生活指導
診断に基づき、症状を改善するための内服薬や外用薬を処方します。
また、日々の生活習慣や適切なスキンケアの方法についてもアドバイスを行います。
保湿の仕方など、皮膚の健康に影響を与える要因について具体的に指導することで、再発予防や症状の安定を目指します。
4. 当院にご相談ください:専門医があなたの肌悩みに寄り添います
菊川内科皮膚科クリニックでは、お子様からご高齢の方まで、あらゆる皮膚のトラブルに対応しています。
患者様一人ひとりの症状やライフスタイルに合わせた丁寧な診察と、分かりやすい説明を心がけております。
「こんなこと聞いてもいいのかな?」とためらわず、少しでも気になる症状があれば、お気軽にご相談ください。
専門医が親身になってお話を伺い、最適な治療法をご提案いたします。地域の皆様の肌の健康をサポートできるよう、スタッフ一同努めてまいります。
気になる症状があれば、まずはご相談を
皮膚は、私たちの体を守る大切なバリアです。
日々の生活の中で、様々な刺激にさらされ、時にはトラブルを起こすこともあります。
「たかが皮膚の症状」と軽視せず、長引くかゆみ、広がる発疹、治らないニキビなど、どんな小さなことでも気になる症状があれば、菊川内科皮膚科クリニックの皮膚科にご相談ください。
早期の段階で適切なケアを行うことが、肌の健康を守り、快適な毎日を送るための第一歩となります。
診察予約は ♪ こちらをクリックしてください ♪
~~監修 医療法人社団 俊爽会 理事長 小林俊一~~
投稿者:
















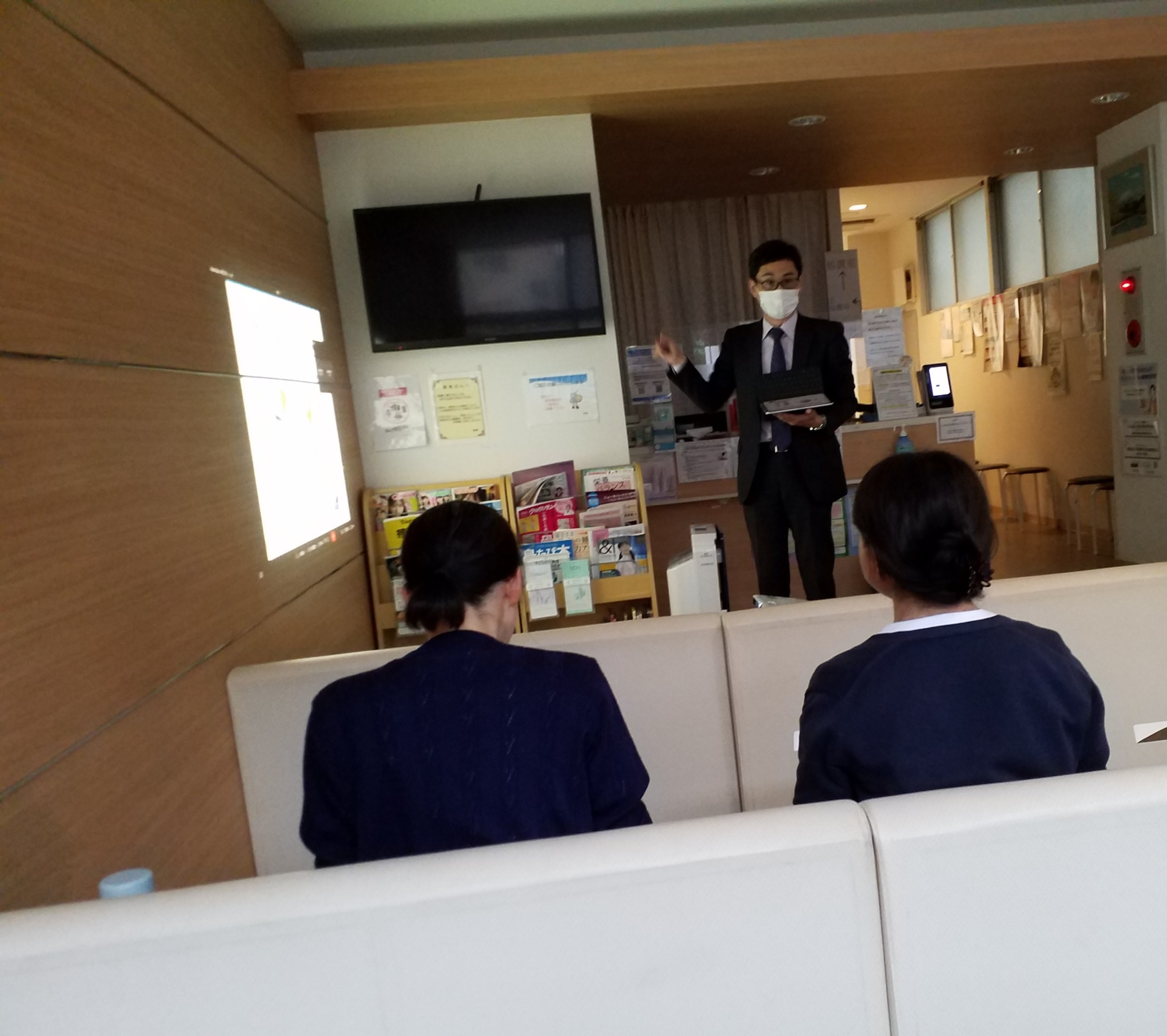

 胃内視鏡検査
胃内視鏡検査