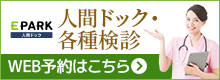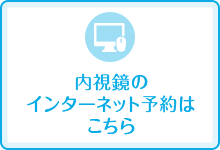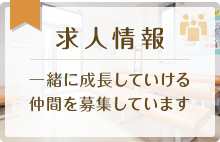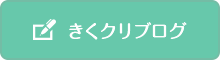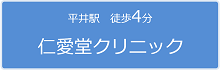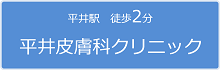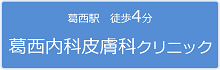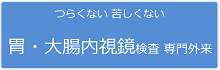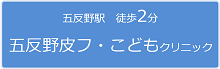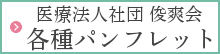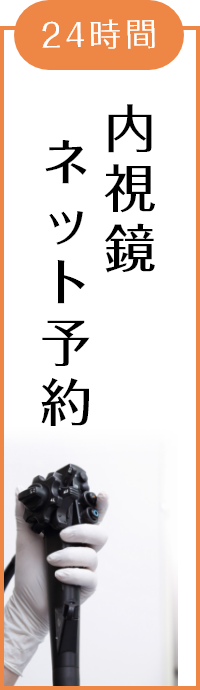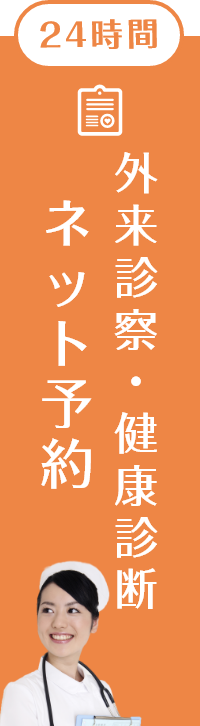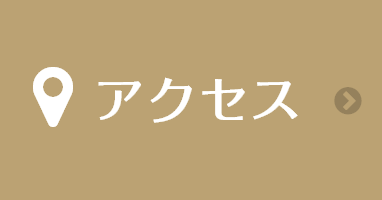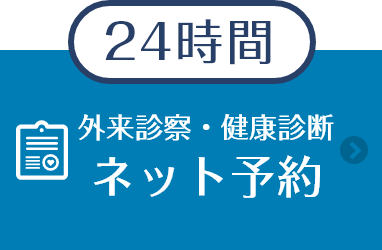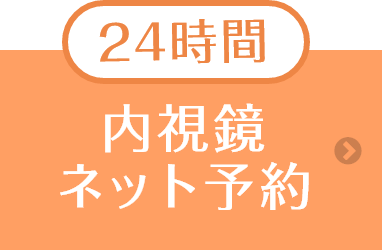RSウイルスについて
2024.01.31更新
RSウイルスについて
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
RSウイルス感染症は、大人も子供もかかる呼吸器感染症です。RSウイルスは、一般的には乳幼児の呼吸器感染症の原因ウイルスと知られていますが、高齢者や基礎疾患のある成人についても症状が重くなり肺炎を引き起こすことがあると報告されています。
RSウイルス感染症はどんな人がかかるの?どうやってかかるの?
◆年齢問わず感染します
RSウイルスは、2歳までにほぼすべての子どもが感染するとされ、その後も生涯にわたって何度も感染と発症を繰り返します。そのため乳幼児だけではなく、成人、特に高齢者にも影響をおよぼす可能性もあります。
喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、心疾患、糖尿病、慢性腎臓病(CKD)などの慢性の基礎疾患がある人や、免疫機能が低下している人は、RSウイルスに感染した場合、肺炎などの合併症を引き起こすこともあります。
◆RSウイルス感染症の感染経路
RSウイルス感染症の感染経路は、飛沫感染・接触感染です。
※麻疹や水痘、結核のように空気感染はしません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
RSウイルス感染症の症状は?
RSウイルス感染症の症状としては発熱、鼻汁などの軽い風邪様の症状から重い肺炎まで様々です。
◆RSウイルスの滞在期間と症状の経過
滞在期間:4~5日
発熱、鼻汁、咳などの上気道炎の症状で発症します。
多くの方は、数日間で回復しますが、一部の方は喘鳴、呼吸困難なども下気道炎の症状が現れ、数日~1週間ほどでかかって回復します。
中には、肺炎などに発展することもあります。
◆特に気をつけたほうがいいのはどんな人?
【大人の場合】
・高齢者、喘息、COPD、心疾患など慢性的な基礎疾患がある人、免疫機能が低下している人
【乳幼児の場合】
・基礎疾患を有する小児(特に早産時や生後24か月以下で心臓や肺に基礎疾患がある小児、神経・筋疾患やあるいは免疫不全の基礎疾患を有する小児等)
・生後6か月以内の乳児
☆RSウイルス感染症は喘息やCOPD、心疾患などの基礎疾患の増悪の原因となることもあります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
どうやって予防したらいいの?
◆RSウイルスの感染が広がりやすい場所
・家庭内(兄弟姉妹・両親から乳幼児へ)
咳などの呼吸器症状がある年長児や成人は、可能な限り0~1歳児とも接触を避ける、または感染を防ぐための対策が重要です。
・長期療養施設(介護施設等)
RSウイルスの集団発生が問題となる場合があり、重症化することもある高齢者が利用する介護施設などでは特に注意が必要となります。
◆RSウイルスの感染を防ぐための対策
・鼻汁、咳などの呼吸器症状があるときはマスクを着用
・手を石鹸と水で20秒以上かけてこまめに洗う
・ドアノブやモバイル機器など、頻繁に触れるものの表面を消毒する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
RSウイルス感染症 よくあるご質問
Q、RSウイルス感染症にかからないためにはどうしたらいいですか?
A、RSウイルスの感染を防ぐには、感染者の咳やくしゃみなどに含まれるウイルスを吸い込むことによる「飛沫感染」、ウイルスがついた手指や物(ドアノブや手すり、おもちゃなど)を触ったりすることによる「接触感染」への対策を行い、ウイルスに接触する機会をできるだけ減らすことが大切です。
Q、RSウイルスに感染した場合、他の人にうつさないよう、何日注意すればいいですか?
A、RSウイルスの感染力は通常、3~8日間持続すると考えられています。
しかし、高齢者の場合には免疫機能の低下からRSウイルスがより長期間にわたって体内に溜まりやすく、咳などでほかの人にうつす可能性がありますので症状のある間は感染を防ぐための対策が大切です。
Q、RSウイルス感染症に一度感染すればまた感染することはありませんか?
A、RSウイルスは、麻疹(はしか)や水痘(水ぼうそう)などのウイルス感染症と違い、一度感染しても免疫が十分に得られません。そのためRSウイルスに一度感染した後も生涯にわたって何度も感染と発症を繰り返します。
Q、RSウイルス感染症は乳幼児や高齢者以外でも合併症を引き起こすことはありますか?
A、喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、心疾患、糖尿病、慢性腎臓病(CKD)などの慢性の基礎疾患がある人や、免疫機能が低下している人の中には、RSウイルスに感染した場合は、肺炎などの合併症を引き起こすこともあります。
Q、RSウイルス感染症に感染したら、何に注意すればいいですか?
A、RSウイルス感染症は、発熱、鼻水、咳などの上気道炎の症状で始まり、多くの方は数日で回復しますが、一部の方では下気道炎の症状が現れます。咳がひどくなる、喘鳴(ゼイゼイ、ヒューヒューとした呼吸音)が出る、呼吸困難となるなど下気道炎の症状に気づいたら、早めに医療機関を受診するようにしてください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
都営新宿線菊川駅より徒歩2分、菊川内科皮膚科クリニックです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
投稿者: