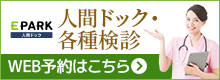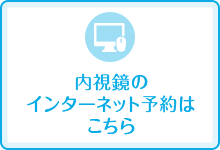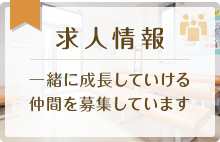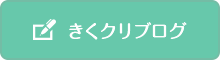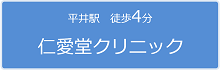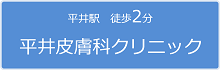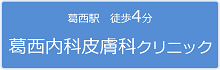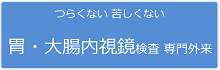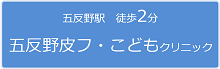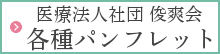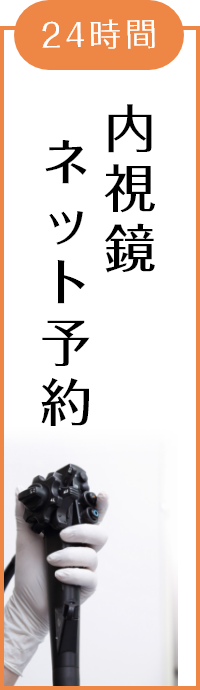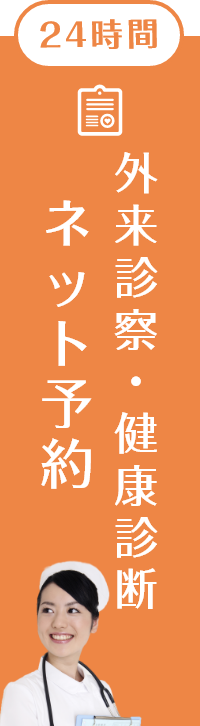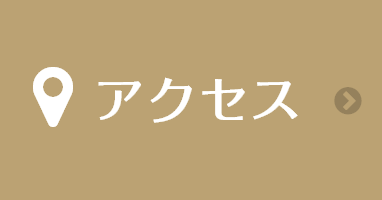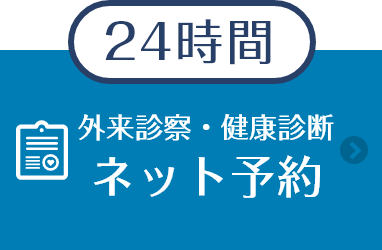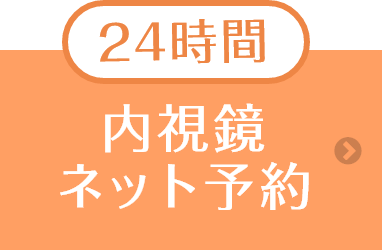「食物アレルギー」と聞くと、身近に感じる方も多いのではないでしょうか
特に、食べることが大好きなお子様がいらっしゃるご家庭では、不安に思われることもあるかもしれません。
今回は、食物アレルギーについて、その基礎知識から日々の生活でできる対処法まで、
患者様の不安な気持ちに寄り添いながら、お伝えできればと思います!!
もし、ご自身やご家族が食物アレルギーかもしれない、とお悩みでしたら、ぜひこの記事を読んでみてください
食物アレルギーとは?
食物アレルギーとは、特定の食物を食べることで、本来は体を守るための免疫反応が、
自分の体を攻撃してしまうことで起こる様々な症状のことです。
通常、食べ物は消化・吸収されて栄養になりますが、アレルギーを持つ方にとっては、特定の食べ物が「異物」とみなされてしまい、
免疫システムが過剰に反応してしまうのです。この反応が、蕁麻疹(じんましん)やかゆみ、呼吸困難など、様々なつらい症状を引き起こします。
症状の特徴
食物アレルギーの症状は、原因となる食物を摂取してから比較的早く現れることが特徴です。多くの場合、数分から2時間以内に症状が出ることが知られています。
症状の現れ方には個人差がありますが、主な症状としては以下のようなものがあります。
・皮膚の症状:全身の蕁麻疹、かゆみ、赤み
・呼吸器の症状:くしゃみ、鼻水、咳、息苦しさ
・消化器の症状:腹痛、吐き気、嘔吐、下痢
・目の症状:目の充血、かゆみ
食物アレルギーが起こる原因
・遺伝的要因:ご両親やご兄弟にアレルギーを持つ方がいる場合、アレルギーを発症しやすい傾向があると言われています。
・環境的要因:食生活の変化や、腸内環境の乱れなどがアレルギーの発症に関わっていると考えられています。
食物アレルギーの種類
・即時型アレルギー:特定の食物を摂取した後、すぐに症状が現れるタイプです。
原因食物の摂取後、多くの場合2時間以内に症状が出ます。
・食物依存性運動誘発アナフィラキシー:特定の食物を摂取した後、激しい運動を行うことで症状が現れる特殊なタイプです。
原因食物を摂取するだけでは症状は出ません。
・口腔アレルギー症候群:特定の果物や野菜を食べた後、唇や舌、喉にかゆみや腫れが現れるタイプです。
花粉症をお持ちの方に多く見られます。
食物アレルギーの発生部位ごとの特徴
・皮膚:最も多く見られる症状で、蕁麻疹や赤み、かゆみなどが全身に広がります。
・呼吸器:咳や喘鳴(ぜんめい:ヒューヒュー、ゼーゼーという呼吸音)など、風邪と間違えやすい症状が現れることがあります。
・消化器:腹痛や嘔吐、下痢などが起こります。特に乳児の場合、血便が出ることがあります。
粘膜:目のかゆみや充血、唇や口の中の腫れなど、局所的な症状が現れます。
食物アレルギーを引き起こす主な疾患
・アトピー性皮膚炎:皮膚のバリア機能が低下しているため、アレルゲンが皮膚から侵入しやすくなります。
乳児期のアトピー性皮膚炎と食物アレルギーは密接な関係があると考えられています。
・気管支喘息:アレルギー体質の方が発症しやすい疾患です。食物アレルギーが、喘息の症状を悪化させる引き金になることがあります。
食物アレルギーを和らげるために自分でできる対処法は?
・原因食物の特定と除去:医師の指示に従い、アレルギーの原因となっている食物を正しく特定し、適切に除去することが最も重要です。
・代替食品の活用:除去食を行う際は、不足する栄養素を補うために、代替となる食品を上手に活用しましょう。
例えば、牛乳アレルギーの場合は、豆乳やライスミルクなどでカルシウムを補給できます。
症状が出た際の応急処置:医師から処方された抗アレルギー薬やエピペン(自己注射薬)を、緊急時に正しく使えるように、日頃から使い方を確認しておきましょう!
受診をした方が良い場合は?
・食物を食べた後、全身に蕁麻疹や赤みが出たとき
・呼吸が苦しい、咳が止まらないなど、呼吸器の症状が現れたとき
・複数の部位に症状が同時に現れたり、意識がもうろうとしたりするとき
・原因が分からず、何度も繰り返して同じような症状が出る場合
どのような検査が必要で、何を調べる?
・問診:いつ、何を、どのくらい食べたか、症状はいつ、どのように出たかなど、詳しくお伺いします。
・血液検査:血液中のIgE抗体の量を調べ、アレルギー反応を起こしている可能性のある食物を特定します。
・皮膚プリックテスト:アレルゲンをわずかに含んだ液体を皮膚につけ、針で少し傷つけて反応を見る検査です。
・食物経口負荷試験:アレルギーの原因と思われる食物を、医師の監視下で少しずつ摂取し、症状が出るかどうかを確認する検査です。最も確実な診断方法とされています。
どのような診断と治療が行われるの?
・診断:問診、血液検査、皮膚プリックテストなどの結果を総合的に判断し、必要であれば食物経口負荷試験で確定診断を行います。
・治療:アレルギーの原因となる食物を特定し、適切な量だけ除去する「食事療法」が治療の基本となります。また、症状を抑えるために抗アレルギー薬などの薬物療法も併用されます。
どのような診察が行われるの?
診察では、まず患者様や保護者の方から、症状がいつ、どのように現れたか、食べたものは何かなど、詳しくお話を伺います。
その上で、アレルギーが疑われる場合は、必要な検査を提案させていただきます。
診察時には、日頃の食事内容や、アレルギー症状が出た時の状況をメモしてきていただけると、よりスムーズな診療につながります。
最後に…
食物アレルギーは、日々の生活に不安をもたらすことがあるかもしれません。
しかし、正しく理解し、適切な対処をすることで、安心して生活を送ることができます。
当院でもアレルギー検査できますのでどうぞお気軽に菊川内科皮膚科クリニックへお越しください

~監修 医療法人社団 俊爽会 理事長 小林俊一~