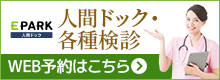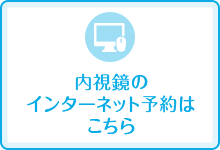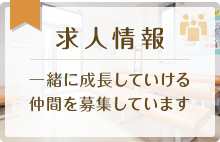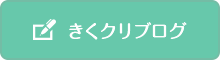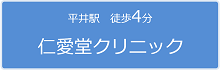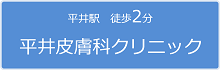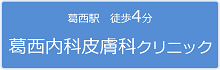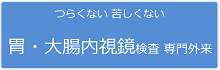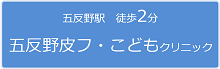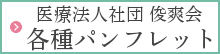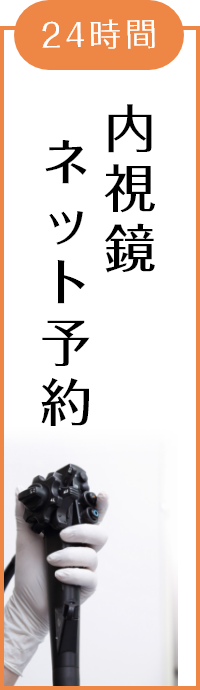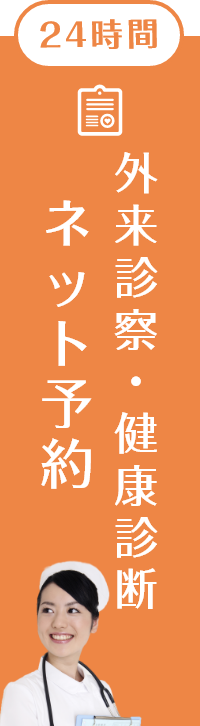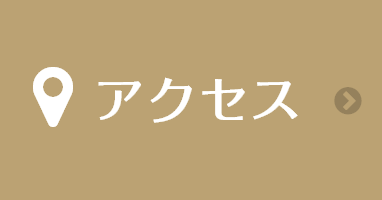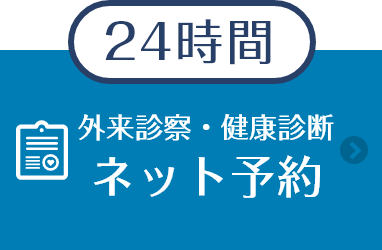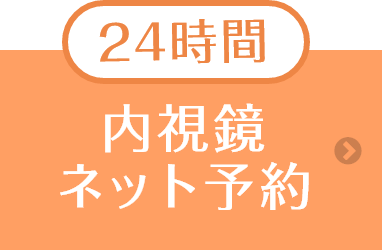「薬ってたくさんあって、どれがどんな効果があるのかわからない」「副作用が心配で、きちんと飲めているか不安」…そんな風に感じたことはありませんか?
毎日飲むお薬だからこそ、正しく理解して、安心して使っていただきたい。
このブログでは、近年注目されている新しいお薬「ウゴービ」を例に、薬と上手に付き合うための大切なポイントをお伝えします。
ご自身の健康を守るために、ぜひ最後までお読みいただき、ご家族やご友人にも教えてあげてくださいね。
当院でも処方可能なお薬となっています。
「ウゴービ」はどのような病気に効くの?
「ウゴービ」は、肥満症の治療薬として最近日本でも使えるようになった、新しいタイプのお薬です。
「肥満症」と聞くと、単に体重が重いだけと思われるかもしれません。
しかし、肥満は高血圧や糖尿病、脂質異常症など、さまざまな病気を引き起こす原因となります。
ウゴービは、このような健康に悪影響を及ぼす「肥満症」を改善するために使われます。
具体的には、体の中にあるGLP-1というホルモンと同じような働きをすることで、食欲を抑え、満腹感を感じやすくする効果があります。
「食べたい」という気持ちを自然にコントロールすることで、食事の量が減り、体重を減らすサポートをしてくれるのです。
どのような種類があるの?
ウゴービは、お薬の成分名である「セマグルチド」を含むお薬の一つです。この成分は、肥満症の治療だけでなく、糖尿病の治療にも使われることがあります。
ウゴービの特徴は、注射薬であることです。毎日飲む錠剤とは違い、週に1回、ご自身で注射して使います。
「注射」と聞くと少し怖いと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、針はとても細く、痛みも感じにくいように工夫されています。
初めての方でも安心して使えるよう、当院では看護師が丁寧に指導しますのでご安心ください。
ウゴービ治療の適応について
ウゴービによる治療は、肥満症と診断された方で、以下の項目を満たす方が対象となります。
必須項目
高血圧、脂質異常症、または2型糖尿病のいずれかの診断を受けている。
追加項目(いずれか一つ)
BMIが35以上である。
BMIが27以上35未満であり、かつ以下11項目の「肥満に関連する健康障害」のうち、合計2つ以上を有する。
2型糖尿病
脂質異常症
高血圧
高尿酸血症・痛風
冠動脈疾患
脳梗塞
非アルコール性脂肪性肝疾患
月経異常・不妊
閉塞性睡眠時無呼吸症候群
運動器疾患
肥満関連腎臓病
※特に2型糖尿病、脂質異常症、高血圧のいずれか1つ以上を満たすことが必須です。
※ご自身のBMIは「体重(kg)÷(身長(m)×身長(m))」で簡単に算出できます。
ご自身の状態が適応となるかご不明な場合は、お気軽にご相談ください。
「ウゴービ」薬の正しい飲み方・使い方
ウゴービは、週に1回、決まった曜日にご自身で注射します。
【正しい使い方と保管のポイント】
いつ使う?
毎週決まった曜日に、ご自身で注射します。食前や食後など、特に決まったタイミングはありません。
どうやって保管する?
冷蔵庫で保管してください。冷凍したり、直射日光の当たる場所に置いたりしないように注意しましょう。
忘れてしまったら?
1日2日程度遅れても大丈夫です。気づいた時点で注射し、その後はまた決まった曜日に戻して使用します。ただし、自己判断は避け、医師や薬剤師にご相談ください。
「ウゴービ」薬の副作用
どんなお薬にも、効果のほかに「副作用」というものが起こる可能性があります。
ウゴービの場合、比較的多いのが「吐き気」や「下痢」「便秘」といった胃腸の症状です。
これらは、体が薬に慣れてくるにつれて、だんだんと落ち着いてくることがほとんどです。
もしも症状がひどい、または長期間続くようであれば、お気軽にクリニックにご相談ください。
また、ごくまれに重い副作用として「膵炎」などが起こる可能性も指摘されています。何かいつもと違う体調の変化を感じた際は、すぐに医師にご連絡ください。
薬に関するよくある質問
Q1. 薬は、お茶や牛乳で飲んでもいいですか?
A. 基本的には、お薬は水かぬるま湯で飲んでください。
お茶に含まれる成分や、牛乳に含まれるカルシウムなどが、お薬の吸収を妨げたり、効果を弱めてしまうことがあります。
Q2. 飲み忘れてしまった場合はどうすればいいですか?
A. 飲み忘れに気づいた時点で、すぐに飲んでください。
ただし、次の飲む時間が近い場合は、1回分を飛ばしてください。2回分をまとめて飲むのは絶対にやめましょう。
Q3. 症状が良くなってきたら、自分で飲むのをやめてもいいですか?
A. 自己判断でお薬を中断するのは危険です。
症状が改善したように見えても、病気の原因が残っていることがあります。必ず医師の指示に従ってください。
最後に…
お薬は、私たちの健康を助けてくれる大切なパートナーです。
しかし、その使い方を間違えてしまうと、本来の効果が得られなかったり、思わぬ副作用が出てしまったりすることもあります。
ご自身の判断だけでなく、専門家である医師や薬剤師に相談することが、安心して治療を進めるための第一歩です。
「このお薬、どう使うの?」「この症状は副作用?」など、どんな些細なことでも構いません。
お薬に関する疑問や不安があれば、いつでもお気軽にご相談ください。
監修 医療法人社団 俊爽会 理事長
日本内科学会 総合内科医 小林 俊一