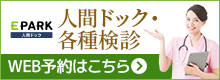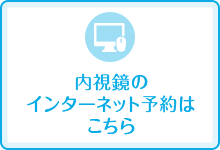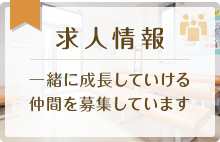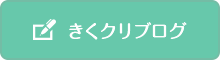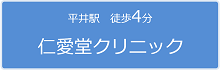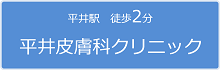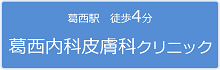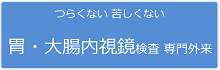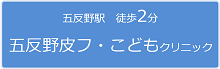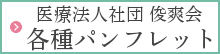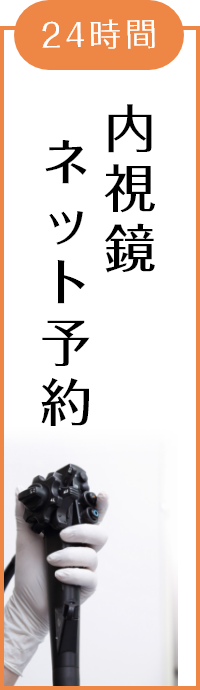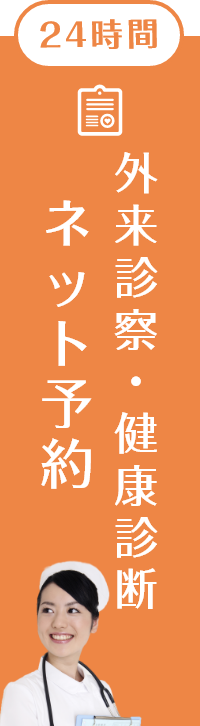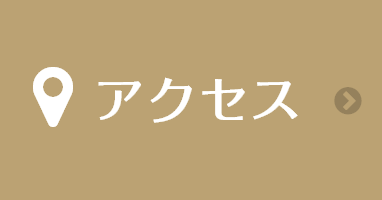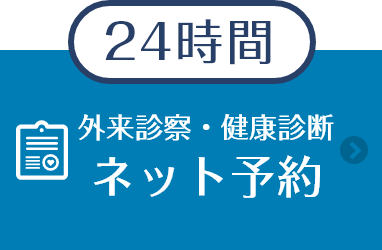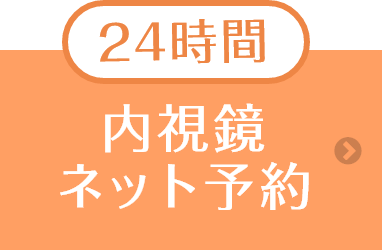アトピー性皮膚炎について
アトピー性皮膚炎とは
アトピー性皮膚炎は、「アトピー素因」をもった人に発症する、かゆみを伴う慢性の皮膚の炎症です。
「アトピー素因」とは、アレルギーを起こしやすい体質のことで、具体的には、以下のような特徴が挙げられます。
・家族やご自身にアレルギー疾患(ぜんそく、アレルギー性鼻炎、結膜炎など)がある
・IgE抗体(アレルギー反応に関わる抗体)を作りやすい体質
このアトピー素因に加え、様々な要因が複雑に絡み合い、皮膚のバリア機能が低下し、炎症が起こりやすい状態になります。
症状は、良くなったり悪くなったりを繰り返しながら、慢性的に続きます。
疫学
アトピー性皮膚炎は、世界中で患者数が増加している疾患です。
特に先進国での発症率が高く、日本では、小児の10~20%、成人の5~10%が罹患していると言われています。
乳幼児期に発症することが多いですが、近年では成人になってから初めて発症するケースも増えています。性差による大きな違いはありません。
季節によって症状に変化が見られることも多く、冬場は空気が乾燥することで悪化しやすく、夏場は汗をかくことでかゆみが増すことがあります。
このように、アトピー性皮膚炎は、その時の環境や体調に大きく左右される病気なのです。
原因
アトピー性皮膚炎の原因は、一つではなく、複数の要因が複雑に絡み合っています。
1. 皮膚のバリア機能の低下
私たちの皮膚は、外からの刺激や異物の侵入を防ぎ、体内の水分が蒸発するのを防ぐ「バリア機能」をもっています。
アトピー性皮膚炎の患者様の皮膚は、このバリア機能が低下していることが分かっています。
その原因の一つとして、フィラグリンというタンパク質が関わっています。
フィラグリンは、皮膚の角質層を形成する重要な成分ですが、アトピー性皮膚炎の患者様の中には、このフィラグリンを作る遺伝子に異常がある方がいることが分かっています。
フィラグリンが不足すると、皮膚の細胞同士の結びつきが弱くなり、スカスカの状態になってしまいます。
その結果、アレルゲン(ダニ、ほこり、花粉など)や刺激物質(汗、石鹸、洗剤など)が皮膚の奥に侵入しやすくなり、さらに、皮膚の水分が外に逃げやすくなるため、乾燥肌になりやすいのです。
2. 免疫機能の異常
アトピー性皮膚炎の患者様は、免疫機能に異常があり、アレルゲンに対して過敏に反応してしまいます。
通常は無害な物質であるダニやほこりに対しても、過剰な免疫反応が起こり、炎症を引き起こします。
3. 遺伝的要因
アトピー性皮膚炎は、遺伝的な要因が大きく関わっています。
両親のどちらか、または両方がアトピー性皮膚炎である場合、お子様が発症するリスクは高くなります。
4. 環境要因
環境要因もアトピー性皮膚炎の発症や悪化に影響を与えます。
・アレルゲン: ダニ、ほこり、ハウスダスト、花粉、ペットのフケなど
・刺激物質: 汗、乾燥、紫外線、衣類の摩擦、石鹸、洗剤、シャンプーなど
・ストレス: 精神的なストレスは、かゆみを増幅させ、症状を悪化させることがあります。
・食生活: 特定の食物がアレルゲンとなり、症状を引き起こすこともあります。
これらの要因が複合的に作用し、皮膚のバリア機能が破綻し、かゆみと炎症の悪循環に陥るのです。
診断
アトピー性皮膚炎の診断は、主に問診と視診によって行われます。
診断のポイントは以下の通りです。
・かゆみがあること
・皮膚炎が慢性的(乳児では2ヶ月以上、その他では6ヶ月以上)に続いている、または繰り返していること
・皮膚炎の分布や特徴(左右対称性、年齢による特徴的な皮疹)
・アトピー素因(家族歴や既往歴)の有無
これらの基準を総合的に判断して診断を下します。血液検査でIgE抗体の値や、特定のアレルゲンに対するIgE抗体を調べることがありますが、これはあくまで補助的な診断です。
治療
アトピー性皮膚炎の治療は、「悪化要因を取り除くこと」と「皮膚の炎症を抑えること」の2つが柱となります。
1. 生活習慣の改善
薬物療法に加えて、日々の生活習慣を見直すことが、治療の成功には不可欠です。
保湿: 乾燥はアトピー性皮膚炎の大敵です。入浴後や、乾燥が気になる時には、こまめに保湿剤を塗るようにしましょう。
スキンケア: 強くこすらず、優しく洗うことが大切です。刺激の少ない石鹸やシャンプーを選び、ぬるま湯で洗い流しましょう。
汗対策: 汗をかいたら、すぐにシャワーを浴びたり、濡れたタオルで拭いたりして、清潔な状態を保ちましょう。
衣類: 肌触りの良い綿素材の衣類を選び、ウールや化学繊維など刺激の強い素材は避けましょう。
アレルゲン対策: 部屋をこまめに掃除し、ダニやほこりを取り除くようにしましょう。
ストレス対策: 適度な運動や趣味を見つけるなどして、ストレスを上手に発散することも大切です。
2. 薬物療法
アトピー性皮膚炎の治療薬には、外用薬と内服薬があります。
外用薬(塗り薬)
(1)ステロイド外用薬
炎症を強力に抑える効果があります。症状の程度に合わせて、弱いものから強いものまで、様々な種類があります。
副作用を心配される患者様もいらっしゃいますが、医師の指示通りに、適切な量を、適切な期間使用すれば、副作用のリスクは最小限に抑えられます。
自己判断で塗るのをやめたり、量を減らしたりせず、必ず医師の指示に従ってください。
(2)タクロリムス軟膏
ステロイドではない、新しいタイプの外用薬です。ステロイドでコントロールが難しい場合や、顔など皮膚の薄い部分に使用されることが多いです。
(3)コレクチム軟膏
JAK阻害剤という新しいタイプの塗り薬で、かゆみと炎症の原因となるサイトカインの働きをブロックします。
2020年に保険適用となり、新たな治療選択肢として注目されています。
内服薬(飲み薬)
(1)抗ヒスタミン薬・抗アレルギー薬
かゆみを抑えるために使用されます。眠気などの副作用に注意が必要です。
(2)ステロイド内服薬
重症の場合に、一時的に炎症を抑えるために使用されます。長期使用は副作用のリスクがあるため、医師の指示を厳守してください。
(3)シクロスポリン内服薬
免疫抑制剤の一種で、重症の患者様に使用されます。
3. 生物学的製剤(注射薬)
従来の治療で効果が見られない、重症の患者様に対する新しい治療法です。
4. 光線療法
紫外線の一種であるUVAやUVBを患部に照射することで、炎症を抑える治療法です。
週に数回、医療機関で治療を行います。
予防、対策
アトピー性皮膚炎は、症状の波があるため、良い状態を保つことが重要です。
1. 日常生活での対策
毎日のスキンケア: 保湿と洗浄を習慣化しましょう。
掻かない工夫: かゆみを感じたら、冷やす、保湿剤を塗るなどして、掻かないように心がけましょう。爪を短く切ることも有効です。
環境整備: こまめな掃除、換気を行い、アレルゲンを減らしましょう。
体調管理: 規則正しい生活、バランスの取れた食事、十分な睡眠は、免疫力を高め、症状の安定に繋がります。
2. 医師との連携
アトピー性皮膚炎の治療は、患者様と医師の二人三脚で進めていくことが大切です。
症状が落ち着いている時でも、定期的に診察を受け、皮膚の状態をチェックしてもらいましょう。
症状が悪化した場合や、かゆみで眠れないなど、日常生活に支障をきたす場合は、すぐに受診してください。
その他
1. 食物アレルギーとの関係
乳幼児期のアトピー性皮膚炎では、食物アレルギーを合併していることがあります。
しかし、自己判断で特定の食べ物を除去することは、栄養不足に繋がる可能性があるため、必ず医師の指導のもとで行ってください。
2. 合併症
アトピー性皮膚炎は、皮膚のバリア機能が低下しているため、細菌やウイルスに感染しやすい状態です。
特に、とびひ(伝染性膿痂疹)やヘルペスなどの感染症には注意が必要です。
また、アトピー性皮膚炎の患者様は、アレルギー性鼻炎や気管支ぜんそく、アレルギー性結膜炎などを合併しやすいことが知られています。
3. 精神的なケア
かゆみや見た目の問題から、精神的なストレスを感じる患者様も少なくありません。ご家族や周囲の理解とサポートが非常に大切です。
最後に
アトピー性皮膚炎は、完治が難しい病気と言われることもありますが、適切な治療と日々のケアで、症状をコントロールし、健やかな肌を保つことは十分に可能です。
つらい時は一人で悩まず、いつでもご相談ください。
都営新宿線菊川駅より徒歩2分、菊川内科皮膚科クリニックです。
~監修 医療法人社団 俊爽会 理事長 小林俊一~